「写真を撮る理由 ⑤」 〜 写真論を読む 〜

「標準・広角・望遠」と3つのレンズを揃えることはできたが、日頃から3本を持ち歩くことはない。普段はひとつのレンズをつけたまま持ち歩き、他のレンズは自宅に置いたまま。どこかに車で遠出をして、本格的に撮るというときは3本をバッグに入れていくが、街中を散歩するときなどは、ガチャガチャとレンズ交換をするのは面倒くさいし、個人的にあの所作はあまり好きではないのだ。
最後に購入した「XF50-140mm」の望遠レンズは、他の2本より遥かに重くて大きいが、写りがいいので持ち歩くことが多かった。被写体を際立たせ、背景をぼかすという「よくある撮り方」ではあるが、いざそれを自分ができるようになるとけっこうハマる。娘を撮るときなどは、ほとんどがその撮り方だった。
自分のPCの中にあるフォルダは、ロードバイクで走ったときの風景よりも、いつしか娘の写真が多くなった。元々は、娘の成長の記録を撮ろうと始めたカメラ。そう考えると、この高価なレンズも購入した甲斐もあるというものだ(ということにしている)。たまに応募するフォトコンテストの写真も、風景よりも娘のポートレートやスナップが増えた。地元のフォトコンでは、そのひとつが最優秀に選出され、まさにレンズ様様という時期もあった。
新しいレンズを手に入れて、新しい撮り方を学び、自分の写真の世界も広がったかのように思えていたが、ふと気づくと似たような写真ばかりを撮っていることに気づく。「自分なりの『テーマ』を持って、同じような被写体を、同じように繰り返し撮っている」とは、少々違う。
「こういうレンズは、こんな被写体をこう撮るといい」という、パターンに陥っていた。レンズに撮らされていたのだ。確かに、新しいレンズでいろいろ試すのは、写真を学ぶためのひとつの過程にすぎないかもしれないが、私は「何を、どう撮りたいのかという自分の意思」が希薄なままに撮っていたように思う。
写真を撮り始めた頃には、まったく考えもしなかった「なぜ写真を撮るのか」という疑問。レンズを揃え、充実したフォトライフを過ごせると思い込んでいた自分に、はからずもその疑問がついてまわるようになり始めた。
気の置けない写真仲間と「なぜ写真を撮るのか」といった話をすることが何度かはあった。「楽しければそれでいいじゃん」というタイプもいれば、「写真は命をかけて撮らねばならぬ」というタイプがいたりして、それはそれで楽しい語り合いなのであるが、写真好きはどうも自分を譲れないところがあるらしく、最後にはお互い疲弊してしまう(笑)。
誰かのアドバイスというものは、とてもありがたいものではあるが、やはり最後は自分の考え方で写真を撮りたい。その方が覚悟が決まるからだ。そう思い、写真に関する本を何冊か読んでみた。技術的なことよりも、写真そのものを語る本をだ。
しかし「写真論」を語るという類の本が、これまたありすぎて読む以前に選べない。写真家として高名な人が書いた「写真論」も読んではみたが、途中で挫折した。そもそも、写真の初心者である自分が、写真の本質に迫ろうかという「論」を読んでも、心に入ってこないのだ。
そんなときに『「写真」のはなし』という本に出会った。いかにも、自分のような悩みを持つ人が飛びつきそうなタイトル。これは、とある写真雑誌で、3人の写真家が連載していた「写真論」で構成されているのだが、その内容はまさに自分の疑問に応えてくれるものであった。
とくに、染谷学さんという方が書いた「写真の話をしませんか?」という連載。自分が難しく考えていた、妙に絡まって解くことのできない糸を、少しずつ解してくれるような「写真論」だった。染谷氏の言葉をもとに、自分なりの「写真を撮る理由」を少しずつ考える作業をしてみた。
今回のこの長いブログも、「写真を撮る理由」を最終的に自分の言葉で書き表すこと、それがひとつの目標であり、それを自分の指針にしたいと考えている。なので、書く内容が多少説教じみたことであっても、それは読む人にというよりは、自分への戒めやルールということであるから、そこはご了承願いたい。
染谷氏の「写真論」は、心揺さぶられるような強い表現や、目からウロコの技術論があるわけではなかったが、ストンと腑に落ちることが書かれてあった。私が今回のブログで最初に書いた「現代はスマホによって誰もが写真を撮れる時代になった」ということを、染谷氏も冒頭で書いていた。
私は、続いて「スマホではなくカメラで写真を撮る理由」が知りたいということを書いた。しかし染谷氏は、続いて次のようなことを書いていた。
…………………………………..
きちんとしたカメラと技術で撮る写真と、スマホで撮る画像には明らかな違いはあるのは間違いないが、写真の長い歴史(機材や表現の系譜)を見たときに、スマホの画像が「写真ではない」とは言い切れない何かがある。
むしろ、「自分は写真をやっている」と公言しているカメラマンが撮るある種の写真よりも、ずっとリアルで、元気で、記録性に富み、自由で工夫があって、残すべき価値も面白さも存分に含んでいる。
コンテストの審査のときに見る、作者の意識と結びついていない、作例の再生産の作品より遥かに写真かもしれないと思うことがある。
…………………………………..
これは、自分にとっても耳の痛い話である。しかし、なぜか腑に落ちる話だった。
何冊かの難解な「写真論」を読み、すぐ挫折した自分にとって、この最初のページに書かれていた内容は、これから先の「自分の写真」について、何かを暗示してくれているような気がした。

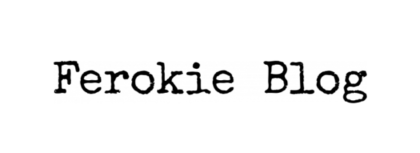










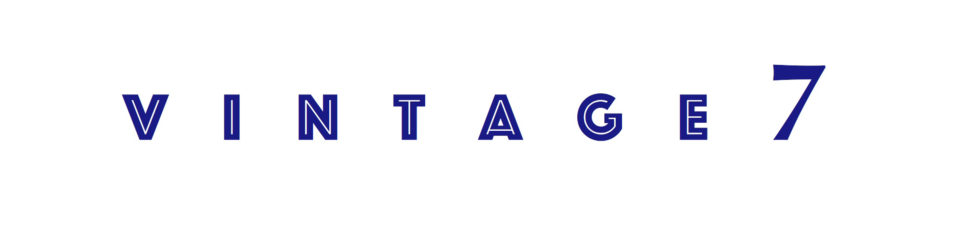
コメントを残す