「茶碗蒸し」「子和え」 「けの汁」
弘前大学の3年生のときから、今現在働いている洋服屋でバイトを始めた。あれからもうすでに30数年。
一度もほかの仕事をすることなく洋服屋をやってきたので、30数年の間、年末年始をゆっくり過ごしたことは一度もない。
ここ数年は、大晦日はお店を休むことにしている。以前は、大晦日の日は初売りの準備をして、15時くらいに上がっていたが、今は30日の夜に残業して準備をしている。
かつて、10何年くらい前だったか記憶は定かでないが、世の中で元旦営業というのがブームになったことがある。中土手町にお店があった頃の話であるが、私の店でも元旦営業をすることにした。
午前中は福袋の販売もあってかずいぶん賑わったけど、昼を過ぎると街は静まり返り、猛吹雪でゴーストタウンのようになったことを覚えている。
2~3度ほど元旦営業をしてみたが、結局やめることにした。やっぱり元旦くらいは休んだほうがいい。
20代の頃は、世の中も浮かれバブルの時代だったので、実家に帰らずに大晦日は飲み明かし、年が明けると大円寺に繰り出すみたいなことをしていた。今ではそんなパワーはまったく持ち合わせていないが、それはそれで楽しかった思い出である。

しかしなんだかんだ言っても、実家のあった鰺ヶ沢に帰ることのほうが多かった。薄暗くなった雪道を走り、親父とお袋の待つ明かりのついた実家に着くとほっとしたものだ。
鰺ヶ沢での年越しは、小さい頃からずーっと変わらぬやり方があった。
まずは、神棚、各部屋、玄関、台所、蔵、小屋、車にお供えをする。
夕方6時頃になると、順番に拝んでいく。親父が拝むのを真似しながら、一緒にくっついて歩く。最後に、お仏壇を拝んで終わる。最後だけ手を叩かないのがなぜだかよくわからなかった。
じつはこの拝んでまわって歩くのが面倒くさくて…というのも、これを終えないと年越し料理にありつけないからだ(笑)
ようやく年越し料理をいただく時間。
私が小さい頃は、お袋が「山海荘」で働いていた。私は「山海荘」自慢の「茶碗蒸し」が大好物で、よく何人分も食べた。あの甘栗は家族の分も集めてまとめて食べたりしたものだ。
あとは「子和え」が死ぬほど好きで。スーパーなどで売ってるのとは違って、「こっこ」がたっぷり入ったやつだ。
そして忘れてならないのは津軽の味「けの汁」。これがないと始まらない。
「茶碗蒸し」と「子和え」そして「けの汁」ばっかりをくりかえし食べていた気がする。
年を越す瞬間はやはり「年越しそば」だ。スーパーで売ってる小さな天ぷらを添えて。
元旦は「大根とニシンの漬物」と一緒に「お雑煮」をいただく。そして「けの汁」(笑)
働き始めてからは、こうして26時間ほどの鰺ヶ沢でのひとときを過ごして、弘前に帰る…という年末年始だった。

お袋が亡くなったあと、親父がひとりになったときの年越しはなんとも言えない気持ちになった。
年越しの料理も、頼んだお寿司とかだった。でも食べる頃には冷え切ってたっけ。
少し飲んだだけでも、すぐ酔いつぶれて寝てしまう親父に毛布をかけて、弟と二人で近所のお宮へお参りに行く。
そんな年越しが10年ほど続いた。
そして、そんな年越しをすることがなくなって10年以上経つ。
大晦日の日に、薄暗い雪道を日本海に向かって走ることは、もうなくなった。
それでもやはり、洋服屋をやっている限りは、のんびりと年末年始を過ごすことはない。
初売りの準備をして、新年2日からの初売りで気合を入れて仕事初めをする。新しい年に向けて、仕事の準備ができるというのはありがたいことだ。
30数年の間、まわりの人達が何日も休んでいるのを見て、「いいなあ~」と思ったことは幾度となくあったけど、このなんとも妙な気持ちで年越しを味わうのもこの仕事ならではと思っている。
一緒に年越しをしていた親父もお袋も、今はいないけれども。
一緒に年を越せる、家族がいるというのはありがたいものだ。
新年が明ける夜中の0時まで、必死に起きている娘を見ているだけでも、年越しっていいなと思う。

2017年も、仕事はあと2日。
新しい2018年に向かって準備をしよう。

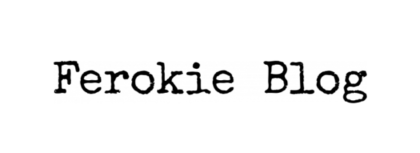





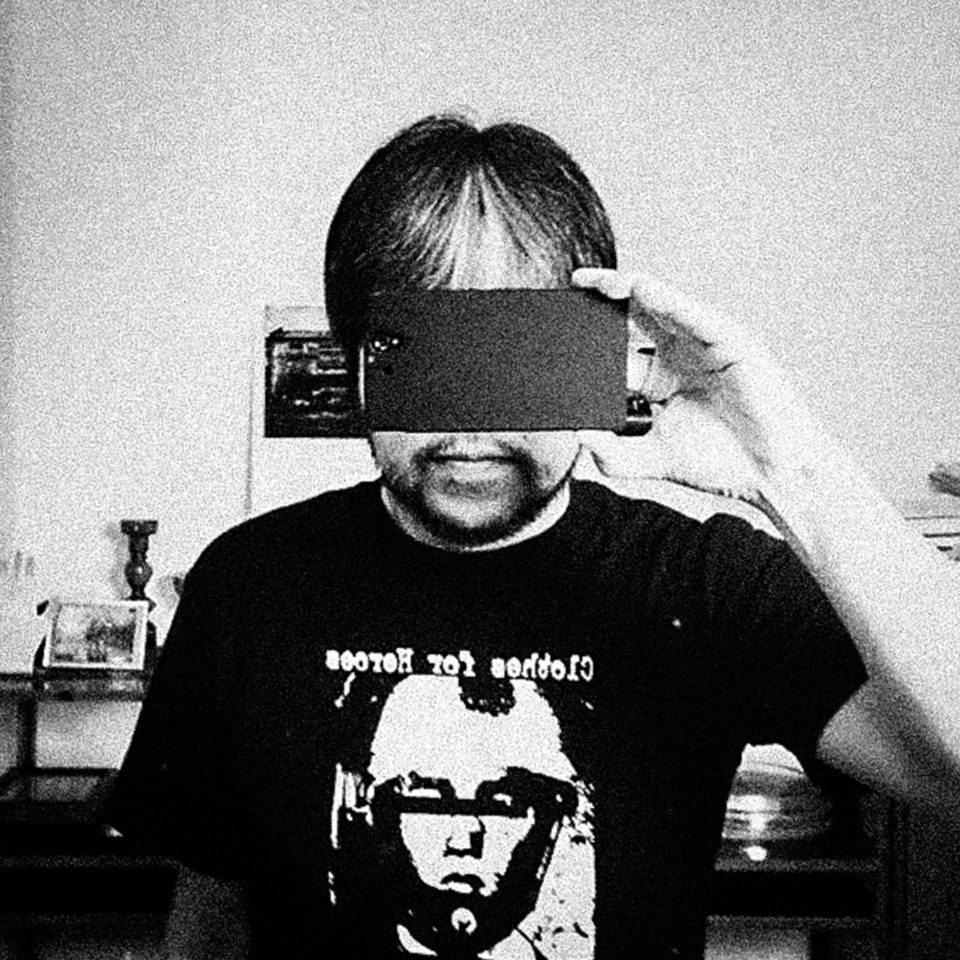




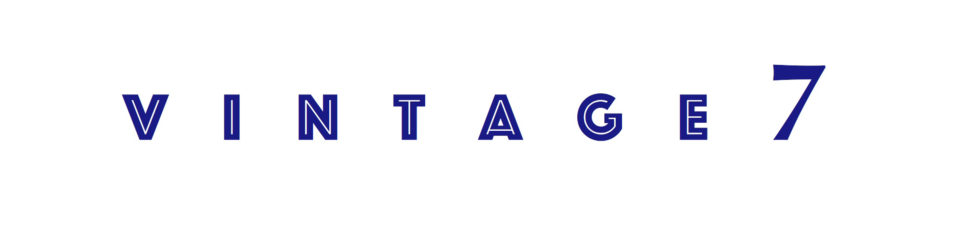
コメントを残す