「 タンポポ 」
カーテンの外が白み始める朝5時頃。「ンニャ〜」と「タンポポ」が私の枕元で鳴いている。私は掛け布団を少しだけ上に持ち上げて空間を作る。彼女は中に入りクルリと丸くなって、すぐにゴロゴロと喉を鳴らした。

娘の今年最後の合唱コンクールが終わると、なんとなくそれに呼応するように季節が秋めいてきた。夏の間は、リビングかどこかで寝ていたらしい猫の「タンポポ」は、昨年あたりから寒くなると私の布団に潜り込むようになった。私も「タンポポ」の温もりをわき腹あたりに感じながら、二度寝するのである。
「タンポポ」は、5年前にウチにきた。そのときはすでに大人の猫になっていた。何軒かのウチを転々としたせいか、ウチにきたときはしばらくの間、怯えたような表情をしていた。今でも時折少し不安げな表情をしているときがある。
私は物心ついた頃から猫と暮らしていた。昔の鯵ヶ沢の実家は下宿屋もやっていて、2階に下宿部屋があり、家族は1階に住んでいた。共同のトイレがあり、そのトイレの奥に物置小屋があった。猫たちはその物置小屋に住んでいた。「猫たち」とは、実際何匹が暮らしていたのかよくわからないからだ。
私が保育園に通っていた頃にいた猫(自分にとっては初代の猫)は「ミコ」といった。名前の通り三毛猫だった。当時はどこのウチも鍵をかける習慣がなく、近所の人が自由に出入りしていたし、猫も勝手に外に出ていたし、腹が減ればウチに帰ってくる…という人間のような暮らしをしていたように思う。仮に玄関が閉まっていても、縁の下から入り、自分なりの通路を辿って物置小屋に帰ってくるのだった。
飼い猫とはいえ、そのような半分野良猫のような暮らしをしていると、知らぬ間にお腹を大きくさせていることは、よくあることだった。物置小屋のダンボールの中で、「ミ〜ミ〜」と鳴く数匹の赤ちゃんと「ミコ」の様子を何度も見に行ったものだ。
生まれて1カ月くらいの子猫たちと遊ぶのが好きだった。「高い高い」をするように、足の裏に乗せて高く持ち上げたりして遊んだ。数匹いる子猫はどこかにもらわれていったりしたが、2代目として「ミケ」が飼い猫として残った。もちろん三毛猫である。しばらくの間、「ミコ」と「ミケ」と母娘三毛猫と暮らした。

その後しばらくして、娘の「ミケ」のお腹が大きくなり、また何匹もの猫が生まれた。その中で黒い猫がウチに残った。名前はもちろん「クロ」だった。3代3匹の猫と暮らしたが、いつしか「ミコ」はいなくなっていた。猫は自分が死ぬときには、姿をくらますと言われているが、やはり「ミコ」の最期の姿を見ることはなかった。
弘前に住むようになってからは、ペットと暮らすことはなかったが、5年前から「タンポポ」と暮らすようになると、自分の小さかった頃を思い出すことが多くなった。
夜、8時過ぎに仕事から帰ると、「ニャ〜」と足下にまとわりついて、クローゼットまでついてくる。布団にゴロンと横になると、腹の上に乗ってきて髭面を舐める。ザラザラとした舌で舐める。よほど髭面が汚れているのだろう。

「ポポ〜」と呼ぶと、どこからか「ニャ〜」と鈴の音とともにやってくる。あと1ヶ月もすると、夜中のうちから「タンポポ」が布団に潜りこみにくる時期になる。そうすると私は少しだけ寝不足になるのだ。

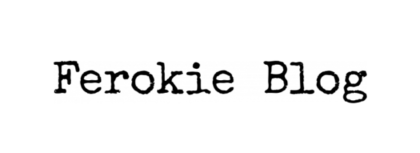










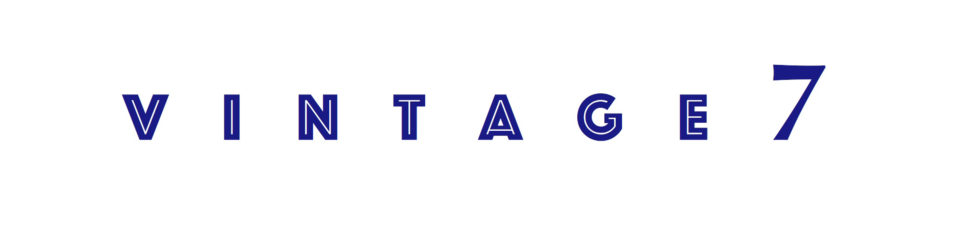
コメントを残す