真夜中のできごと
夜中の23時半、娘が眼に涙を浮かべていた。
「何、泣いてるの?」と訊くと、「何、書いていいかわからない…」と言う。
数日前に修学旅行から帰ってきた。その旅行での『自由見学の感想を書く』という宿題が残っていた。ページの半分は書いたが、あと少しを書けないらしい。
「何、書いていいか…思い出せない…」 「だから、忘れないうちにすぐ書いたほうがいいよ、って言ったじゃない」
私がそう言ったせいだろうか、それとも自分の不甲斐なさを感じたせいだろうか…いや、いろんな感情がごちゃ混ぜになったのだろうか、いよいよ本格的に泣き出した。
「どれ、お昼ご飯のことは?」「書いた」
「じゃあ、函館の夜景を見たことは?」「書いた」
大概のことは書いたらしい。「そんなに完璧に書かなくても大丈夫だよ。少しくらい行が余っても先生も怒らないから」
学校の先生が聞いたら、私が怒られるかもしれない。しかし、言い方は悪いが、手を抜くことも大切だ。どんな人間でも、適度に手を抜かないと神経がやられる。
そのかわり、好きなことは妥協しないでとことんやればいいんだ….と思いながらも、手抜きだらけの人生を歩んできた自分が言うことに、少し違和感を感じた。

娘は泣きながらも、なんとか宿題を書き終えた。時計は0時半になっていた。
「おお、頑張ったな。シャワーは明日の朝にして寝るべ」
布団に入っても、娘はまだ泣いていた。私は隣に寝て、頭を撫でた。
「どした? もう泣かなくていいから」 と言うと、娘が泣きじゃくりながら言った。
「いつも…いつもパパを困らせてばっかりなのに、パパはいつも許してくれる。ごめんなさい…ごめんなさい…」
なんども声をしゃくりあげながら言った。私は少し驚いた。そして、娘に言った。
「パパは何も困っていないよ。いつも一緒に遊んだり、歌ったり、幸せな気分を感じているのはパパのほうなんだから」
「うん。ありがとう」 「もう泣かなくていいから。もう寝ろ」
しかし、娘はなかなか泣き止まなかった。
「よし、ほら、乗っかれ」 と、私は娘をおんぶしようとした。
「え…いいよ。重いよ」 「クラスで一番軽いくせに、何言ってるのや」
おんぶをしたのは何年ぶりだろうか。クラスで一番軽いとはいえ、確かに娘は重くなっていた。
私は歌を歌った。今、合唱部で練習している「てぃんさぐの花」という沖縄の民謡だった。それは、親が子を思う、子が親を思う、叙情的な歌だった。
二人で練習しているのはアルトのパートだったので、その旋律は決してメロディアスではなかった。でも最後まで歌った。
子守唄にはならぬようだったが、少しだけ気持ちは落ち着いたようだった。
再び布団に入っても、しばらくの間「ひっくひっく」と泣いていたが、10分ほどすると寝息にかわっていた。

時計はすでに1時になっていた。私も早く眠りに就きたかったが、なぜか眠れなかった。
すぐ隣で寝ている娘の顔を見た。嬉しいというのでもなく、悲しいというのでもない。うまく言い表せない妙な気持ちが、もやっと身体の中にあった。
無理やり眠ろうとして、私は目をつむった。

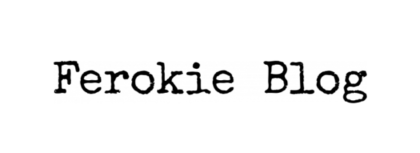










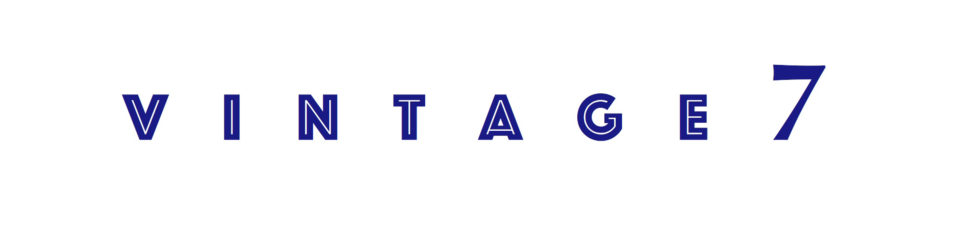
コメントを残す