ツール・ド・ツガル / 津軽富士見湖 〜旧水元小学校
ほとんど桜が散ってしまった弘前の街。
山の方はまだ咲いているかと思いきや、知り合いのSNS情報によると山の桜もだいぶ散っているらしい。
いつもの年であれば、街の桜が散る頃は酸ヶ湯温泉を目指してヒルクライムをしていた。あの辺りはちょうど咲いているのだ。
今はあの高さまで上る自信がない。ただ、ダラダラしていると一生ヒルクライムできぬ身体になってしまいそうだ。
「まずは動け」とばかりに、物置からロードを引っ張り出し、岩木山方面に向かって走ることにした。
風が強い。
岩木山から吹き下ろしているのか、それとも西の海からの風なのか…とにかく風が強い。
西の方角に向かって走り出したことを少し後悔しながらペダルを回した。
鶴田の写真仲間が写真展を開催していることを思い出した。
確か「津軽富士見湖」の近くにある古い校舎でやっているはずだ。そこへ行ってみよう。
清野袋から三世寺と岩木川沿いの道を走る。
それにしても風が強い。強すぎる。
酸ヶ湯までのヒルクライムをしているのと同じくらいの負荷を感じる。
昼で学校が終わったのか、向こうからママチャリに乗った中学生がものすごいスピードでやってくる。
若くパワーが有り余っているのかもしれないが、明らかに彼は追い風に乗っていた。
その証拠に、私の前方にいたママチャリの中学生たちは、向かい風に対抗できずにチャリから降り押していた。
「これでも一応チャリダーなんだ」と言わんばかりに、トロトロの速さで私は彼らを追い越した。
平地とはいえ、普段の半分ほどのスピード。
左前方に見える岩木山のカタチは三角形にはならず、まだいびつなカタチをしていた。
林檎の花が咲き始めた、新和から三和の岩木川沿いを走る。
少しずつではあるが、岩木山のカタチが二等辺の三角形に近づいているのがわかる。
勘を頼りに、ひたすら西に向かって走っていると、視線の向こうに堤防の柵が見えた。
いつの間にか「津軽富士見湖」に着いていた。

津軽富士と湖
「津軽富士見湖」は、青森県最大の人造湖であり、堤長は延長4.2 kmで、日本最大の長さである。
岩木山を水源とする自然流水の貯水池で、岩木山(津軽富士)の見晴らしが良いために、古くから「津軽富士見湖」の愛称で親しまれている。
「廻堰大溜池(まわりぜきおおためいけ)」は、この貯水池の正式名称である。(Wikipediaより)
湖の向こうにそびえる津軽富士。美しい木々や野鳥。
四季折々、花鳥風月満載のこの湖は、多くのカメラマンを引き寄せる。
風が強いせいか、湖面はまるで海のように波立っていた。
風が強すぎるせいか雲はほとんどなく、蒼すぎる空が山を際立たせていた。
振り返り、反対側を見ると、緑色の大きな屋根が見えた。おそらくあれが旧水元小学校だろう。
私は再びペダルを回して、緑色の屋根の方に向かって走り出した。

鶴田町歴史文化伝承館(旧水元小学校)
「水元小学校」は平成16年に廃校となったが、地域住民から建物の保存の要望が多く、現在は鶴田町の「歴史文化伝承館」として活用されている。
ヒバ造りの木造校舎が現存するのは全国でも珍しく、町の文化財の指定を受けているらしい。
玄関から入ると職員の方だろうか、気さくな感じの若い女性の方が迎えてくれた。

渡り廊下から体育館を望む

芸術作品のような木造構造の体育館

木造の階段も美しい
50年ほど前、小学生だった自分が通っていた小学校も、このような感じだったろうか。
ノスタルジックではあるが、それ以上に、この古い木造校舎が美しい佇まいを見せていることに年月の持つ重さを感じた。
体育館と反対側に歩くと、「鶴田写真クラブ写真展」の会場があった。
以前、弘前で一緒に写真展を開催したサイトウタカシ氏を始め、鶴田町で活躍する写真家の方々の作品展。
津軽富士見湖や野鳥の写真も多く見られ、地元の自然や風習を被写体とする作品がたくさんあった。
サイトウタカシ氏の作品は、さすがプロだけに素晴らしい。物語性を感じる写真だ。
そして、私が尊敬する津軽の写真家 神秀次郎氏の作品は、やはり素晴らしかった。

神秀次郎氏の作品
神氏は私よりはずっと歳上で、五所川原高校音楽部の大先輩でもあった。音楽部の先輩であり、写真の大先輩。
氏の写真集を拝見したことがある。それは岩木山の写真集だったが、よく見られるような岩木山の写真はなかった。
ほとんどがモノクロで、そこには岩木山にたいする畏れがあり、心が突き動かされるような写真だったことを憶えている。
会場をぐるりと数回まわり、私は美しい木造校舎をあとにした。

外から見た体育館
何か妙にスッキリとした気持ちになり、五所川原方面に向かって走り出した。
津軽富士見湖から東へと向かう道は、気持ちの良い追い風になっていた。

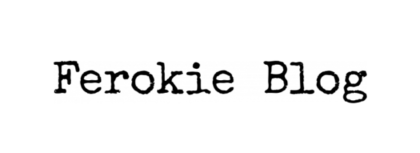





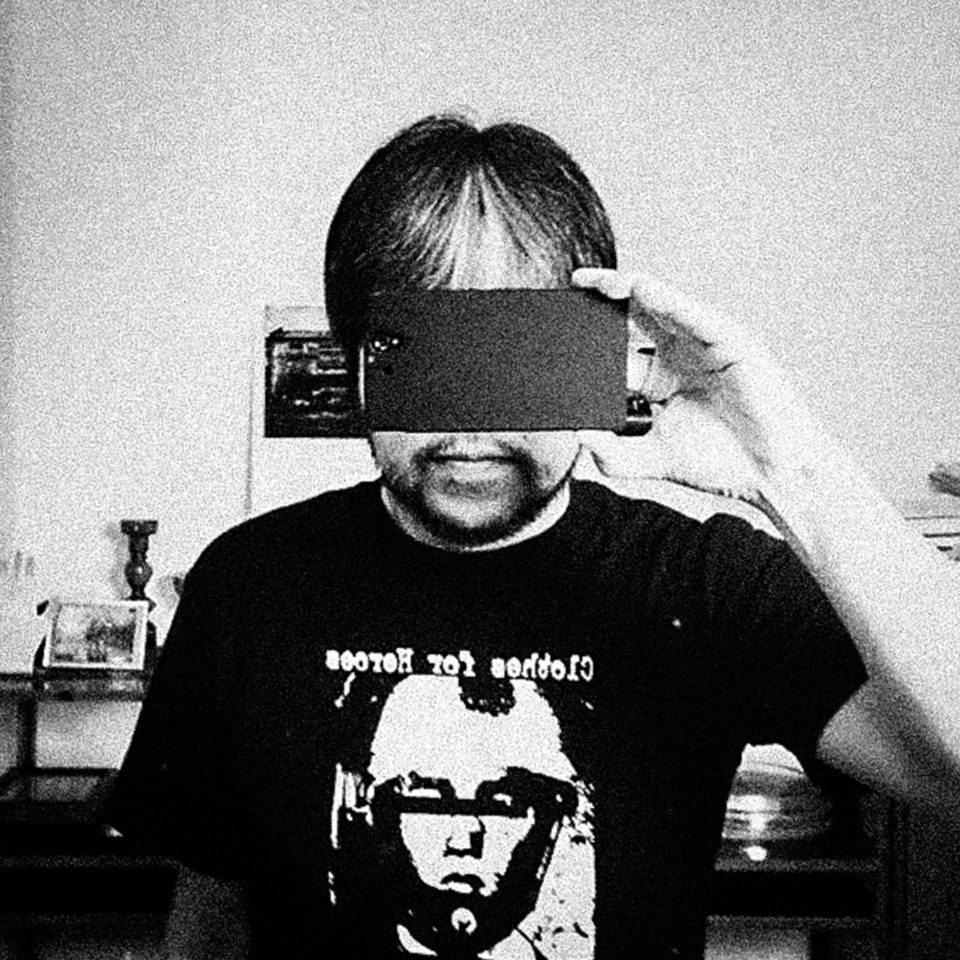




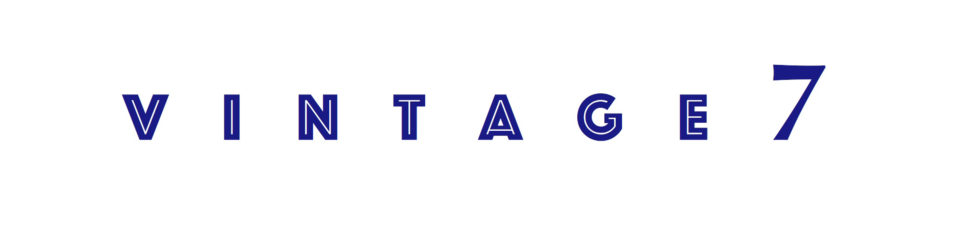
コメントを残す