初めての音源 / 【 声楽アンサンブルコンテスト 】より
「写真」は、撮った作品を見ると、その人がどんな写真を撮るのかが少しはわかる。
「ロードバイク」は、走るのが遅かったとしても、目的地に着いたときの記念写真を見れば、どこまで走ってきたのかがわかる。
「ファッション」は、その人がどんなアイテムを選び、どんなスタイリングをしているのかを見れば、雰囲気がつかめる。
「ラーメン」は、画像と食べた人の感想やコメントがあれば、なんとなく想像がつく。
そういう意味で、「視覚」から入ってくるビジュアルは、人間が物事を判断する上でとても重要な役割を担っている。スマートフォンが普及し、誰もが高解像な「画」を撮ることができる現在において「視覚」は欠かせない。
上に挙げた自分が趣味としているアートやスポーツ、そして食べるもの。その情報はビジュアルから入るものが多い。
しかし「音楽」は違う。音楽情報誌やインターネット上で「この音楽がいい」「このバンドが凄い」と書かれてあっても、果たして自分にとってはどうなのか。
仮に映像を観たとしても、演奏をしている姿を見ただけでは、そのアーティストが奏でる音楽がどんなに凄いのかは伝わってこない。
「音楽」は「聴覚」から入ってくる情報が大切だ。もちろん、演奏するそのビジュアルが心を打つことは多々あるが、それは「音」があってのことだ。
高校時代、大学時代と歌を歌ってきた。どちらも60〜80人ほどの合唱団。昨今では、このくらいの規模の合唱団は少なくなったらしい。
社会人になってしばらくお休みしていたが、15年ほど前から再び歌い始めた。10〜15人ほどの小さなアンサンブルで歌うことが多くなった。
そして一昨年、娘が合唱部に入部した。私もこれまでの経験を生かせないだろうかと、指導にお邪魔するようになった。
最初の頃は「なんだこの父兄は?」と思われていた。当然だろう。いきなり現れた髭のオッさんが歌の指導をしている。「歌を指導するふりをした変質者ではないか?」そう思われたかもしれない。
「本当に歌などやっているのか?」「ただのカラオケ好きじゃね?」
SNSを始めて7〜8年ほど経つ。ブログも書いて2年。
自分の撮った「写真」は数えきれないほどUPした。「ロードバイク」で200km走破の龍飛崎もUPした。高血圧で食べるのを控えるべき「ラーメン」は何杯UPしただろうか。
「歌」は初めてだ。子どもたちの演奏をUPしたことはあるが、自分が歌う演奏は初めてだ。
あまりの下手くそさに腰を抜かすかもしれない。だが、これもオッさんの記念。

今年の3月。福島市で開催された「声楽アンサンブルコンテスト全国大会」
男声13名のひとりとしてステージに上がった。参照→ 【 声楽アンサンブルコンテスト全国大会2019 】 福島市音楽堂 その2
「Ubi Caritas」と「Ave Maria」 2曲とも、古くから教会で謳われる詩を、近現代の作曲家が書いた「宗教曲」である。最大6声部という難解なハーモニーで構成されている。
男声特有の厚みのある響きを、ぜひ、ヘッドホンかイヤホンの大音量にてお聴きください。(自分の声は、低音でうごめいていて聴こえづらいので…)
※ 映像は、私が撮った津軽の四季の風景です。音楽とは全く関連がありませんこと、お許しください。

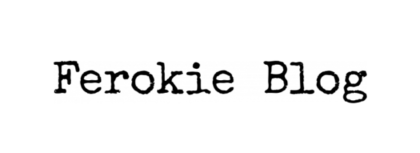



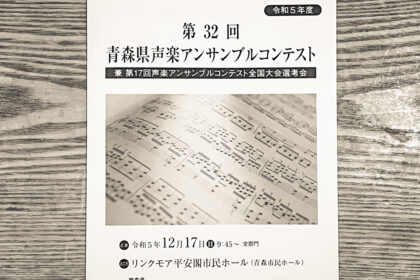

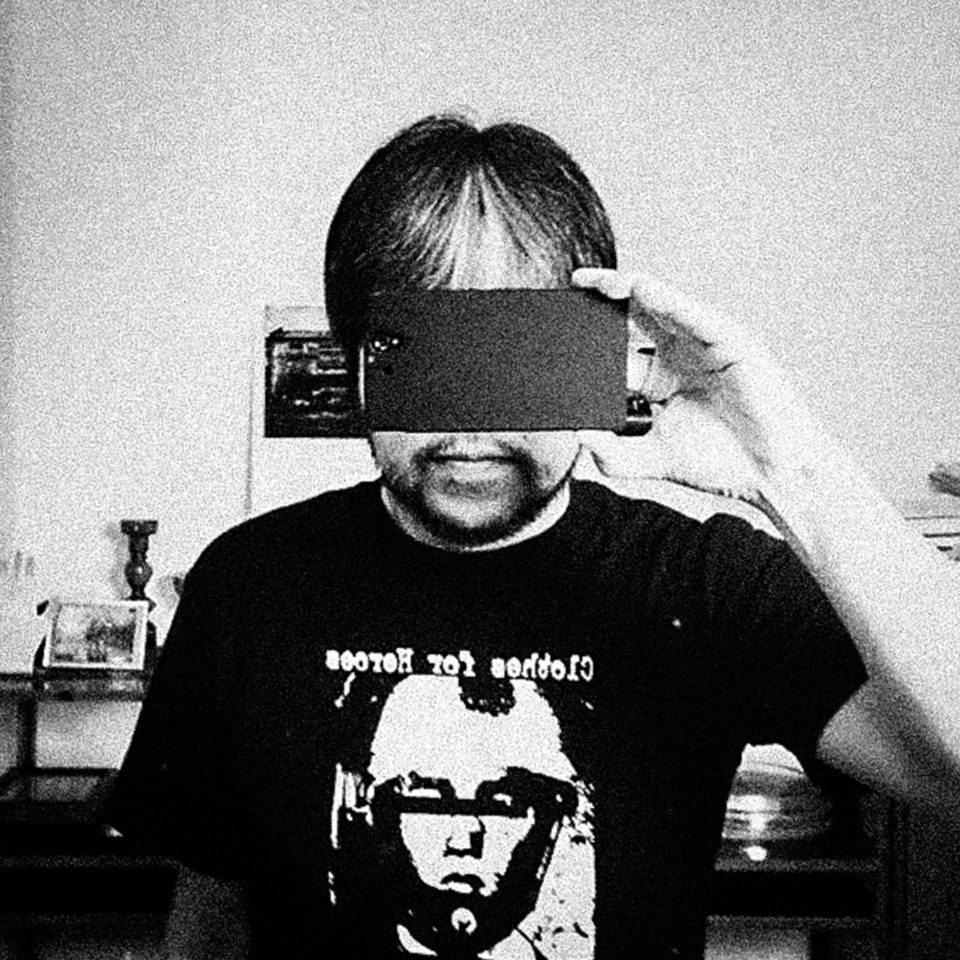





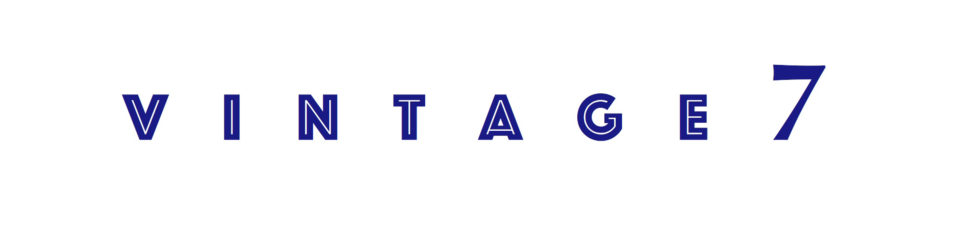
コメントを残す